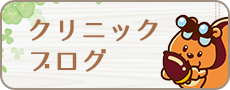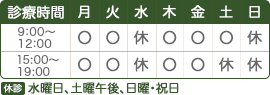嚥下障害(えんげしょうがい)
最近増えている高齢者の誤嚥性肺炎
最近、高齢の方の誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)という言葉をよく耳にすることがあると思います。
この誤嚥という言葉は、平たく言うと飲み込む予定の御飯などの食塊が、気管や肺のほうへ流れてしまうことを意味しています。
でも、普通そんなことになれば、すごくせき込んで苦しいはずです。何故そのようなことが増えているのでしょうか?
理由は単純で、御高齢の方が増えているからです。
加齢とともに、食べる動きにも筋力低下が影響
ご飯を食べて飲み込む際、様々な筋肉の動き、神経の反射、咽喉頭感覚の反射が起きています。
これらは意識するレベルにのぼることなく、スムーズにできるものなのですが、加齢とともに、のどの感覚低下・喉の筋力低下が起きます。
これらにより飲み込むときにおきる誤嚥のパターン、飲み込み終わった後に喉に咀嚼した食物塊の遺残が多くなり、誤嚥につながるパターンがあり、いずれにしても誤嚥性肺炎につながっていきます。
誤嚥性肺炎の対策
年齢的に感覚低下が起きてくることはやむを得ないですが、筋力低下についてはある程度対策を練ることができます。
一番わかりやすい形としては、
「よく食べること」そして「よくしゃべること」です。
食べることについては、特にたんぱく質を意識してほしいと思います。
加齢に伴い全身の筋力低下が起きますが、のどの筋肉についても例外ではありません。
しゃべること、食べることは、その行為そのものが喉の筋肉を刺激することにつながり、そしてたんぱく質を摂取することで喉の筋力をつけることにつながります。
症状の程度に合わせて適切な治療法を選びましょう
ただ、実際に嚥下障害の程度が強い方の場合、そのような対策をしたとしても症状がすぐに改善するわけではありません。
嚥下障害の程度が悪い方は、その程度に応じた食事形態の評価を行う必要や、あるいは適切なリハビリテーションを受ける必要があります。
また、パーキンソン病などの神経筋疾患に伴い嚥下障害をきたすケースもあります。
嚥下障害の評価は耳鼻咽喉科で行うことができます。
私も大学病院勤務をしていたときは、嚥下チームに属していたため、病棟の患者様の嚥下障害の評価、リハビリテーションについて他の医師達と、そして言語聴覚士の方々と共に介入しておりました。
まずは診断をして、結果から必要な検査、紹介、方針をお伝えします
ただ、当院はクリニックのため、嚥下内視鏡検査や造影検査などは困難で、またリハビリテーションについても言語聴覚士の方が院内にいるわけではないため、施行は困難です。
咽喉頭所見を確認し、全身の評価から専門病院への紹介が必要かどうかの判断を行うことは可能です。
また、程度の軽い方の場合、ある程度の指針・リハビリテーションの方針についてお伝えすることは可能です。
- 飲み込みが難しくなってきた
- 食事中のむせこみが多くなってきた
- 誤嚥性肺炎になり、耳鼻咽喉科で一度診てもらったほうがいいといわれた など
もし上記項目にあてはまる患者様がいらっしゃいましたら、ぜひ当院を受診してください。お待ちしております。


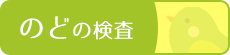
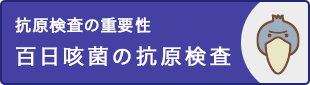
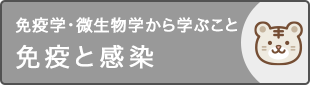
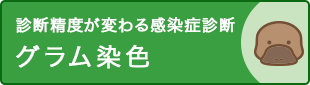
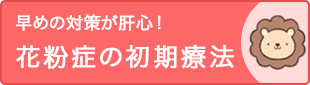
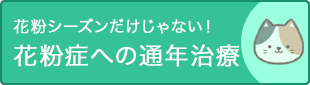

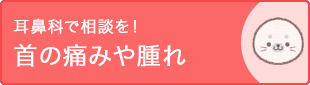
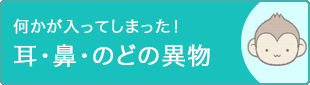
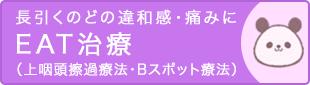
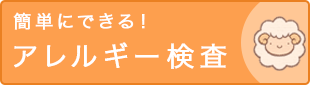
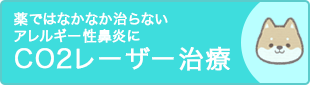
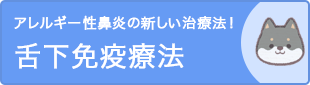
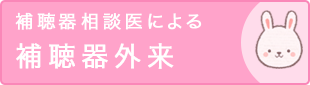
- 耳の病気
- 急性中耳炎
- 慢性滲出性中耳炎
- 良性発作性頭位めまい症
- メニエール病
- 突発性難聴