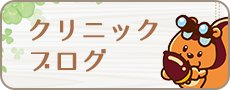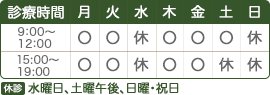免疫と感染、アレルギーについて
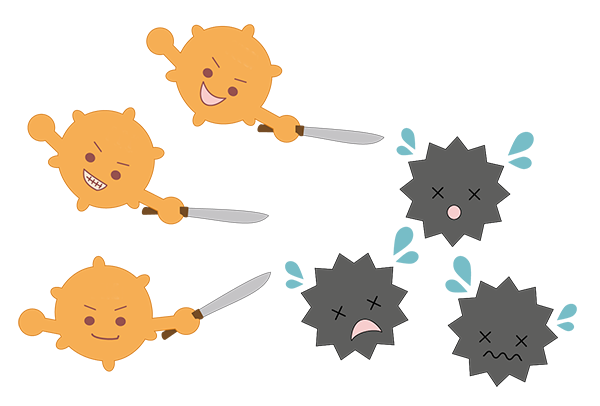
日常診療の中で、より詳しい病態についての質問があった際に、できる限り詳細に返答をするように心がけておりますが、医学の知識は膨大であり、患者さんにそれが伝わったのかどうか、私の話は難解な内容ではなかったか、自問自答する事は多々あります。
のど風邪で当院を受診される方の多くは、恐らく私の細かい説明よりも、端的に「何の病気で、何の薬が必要か」といった事が知りたいこととは思います。
しかし中には詳細に聞きたいという方もおられます。
特に初めてお会いする方の場合、それを一瞬で判断することは難しく、極力丁寧に診察内容をお伝えするようにしておりますが、文面で私の考えていることを事前に共有できるのであれば、それは診察の一助となるのではないかと思い、執筆することとしました。
大事なのは、免疫について知ること、そして細菌やウィルスについて知ること、この2点なのです。
いずれか片方だけでは、知識の偏りが生じ、病態の把握に支障を来すことになります。
ただし、免疫学・微生物学いずれも知識量は非常に膨大であり、これから先は、少しずつ単元化しながら解説していこうと思っています。
免疫と微生物の基本的な関係性
まずは、大前提として、免疫の基礎と、微生物学の基礎からです。
ずんだもんの動画で以前伝えましたが、免疫と微生物について、概ね一対一対応と考えられる関係性については、ウィルスや細胞内寄生生物に対し1型免疫、細菌などの細胞外寄生生物に対して3型免疫、寄生虫など、かなり図体の大きな微生物に対し2型免疫という基本的な理解が必要です。
いきなり難しい話で申し訳ありませんが、これは算数で言うところの1+1=2みたいなものなので、どうしても理解してもらわなくてはなりません。
そして、1型免疫と3型免疫は割と仲が良くシフトしあいますが、2型免疫とそれ以外の免疫はあまり仲が良くないので、基本的には拮抗しあうということも大事です。
2型免疫とアレルギーの関係
現代の日本において、寄生虫感染というものはほぼ罹患することのない疾患となりました。
では2型免疫というものはほとんど利用されなくなったかというとそんなことはなく、現代においてはアレルギーという形で我々を困らせる形で存在しています。
本来は寄生虫に対する免疫なのに残念なことではあるのですが、これについてはいずれ執筆しますので、今回は割愛します。
のど風邪とウィルス感染の基本
日常生活において、のど風邪と言えば、一般的にはライノウィルスやヒトメタニューモウィルスなど、RNAウィルスが咽頭粘膜にとりつき、感染を起こすことで生じるものと判断されています。
例外的に溶連菌という細菌は、同じように人から人へ移り感染を広げる面があるので、のど風邪だから全部抗菌薬が要らないというのは違いますが、概ねウィルス感染が最初に起きると思っていただいて良いです。
ウィルスは細胞内に自身のRNAなりDNAを放出しコピーを多量生産し、寄生した細胞で多量の子ウィルスを産生した後、細胞を破壊して周囲に広がっていきます。
感染を起こした上皮の細胞も、ウィルスに感染したことを感知できるレセプターを用意はしており、感知すればそれを免疫細胞に知らせるシステムがあるのですが、ウィルスも賢いですので、それを巧みに表に出させないようにしたりと、色々と種類毎に性質が異なっています。
潜伏期間と1型免疫の発動
ウィルスが感染を狙っている相手を宿主と言います。
宿主の細胞内では、ウィルス感染が起きても、すぐに症状が出るわけではありません。
暗黒期といって、ウィルスの増殖が十分量に到達するまでには症状が出ない期間があり、いわゆる潜伏期間というものが発生します。
これがウィルス毎に異なるため、いつどこでウィルス感染をもらったのか、同定することが難しかったりします。
いずれにせよ、ウィルス感染により局所の細胞の多くは破壊され、免疫が駆動する状況となります。
これが1型免疫というものになります。
概ね大事な仕事を任されているのは、樹状細胞、マクロファージ、CD4陽性T細胞、CD8陽性T細胞、形質細胞などです。
詳しくはもっと色々な機序がありますが、それはいずれ執筆することとします。
概ね5日~7日ほどで、こういったウィルスなどの1型免疫が駆除する疾患は、けりがつくことが多いですが、実際には変異したウィルスの残党狩りのようなものがもうしばらく続く、とはされています。
ただ、概ね症状は落ち着いてくるのがそのくらいの時期で、いわゆる免疫力が強いね、などと言われる方の場合、だいたいこの程度で症状が落ち着き、人によっては病院を受診することもなく治癒するのではないかと思います。
問題はこれからです。
ウィルス感染後の粘膜上皮は、通常の安定した粘膜上皮とは状況が異なっています。
腸には腸の、喉には喉の、鼻には鼻の常在菌がおり、概ねある程度の傾向があるのですが、実は個人差が結構あります。
その中には、腸の中の善玉菌といわれるような、比較的悪さをしない細菌もいれば、悪玉菌といわれるような、状況によっては悪い影響を及ぼす細菌もおります。
鼻やのどにおいては、肺炎球菌・インフルエンザ桿菌・モラクセラカタラーリス・溶連菌などがいわゆる悪玉菌として指摘して良いと思いますが、これらがのさばり易い状況となります。
二次感染のリスクと受診の目安
これらの細菌が、様相が一変した粘膜上皮上で、領域を拡大していきます。
この時の拡大しやすさ、3型免疫の駆動の速さ・あるいは貪食力の強さ・維持がどの程度できるか、あるいはNO産生能力の程度、あるいは栄養状態やストレスの加減によるステロイドホルモンでの免疫抑制状態の有無など、様々な要因により、急性副鼻腔炎へ移行していく、あるいは他の細菌感染の病態へ移行していくことが一般的には多いです。
ですから、熱が出たり、のどが痛かったりして、それが1週間前のことで、今ものどが痛い、あるいは痛くはないけど痰が出たり咳が出たりする、などといった事がある時点で、すでにそれはウィルス感染による風邪ではないのです。
ここがおそらく一番誤解がある部分で、特に病識があまりない方ほど、3週間前から、とか、あるいは1ヵ月以上前から風邪が治らないんですよね~と言われたりします。
風邪をひいて1週間経過しても改善していないなら、耳鼻咽喉科を受診してください。
今後の執筆について
少し長くなりましたので、今回はここまでとします。
次は細菌の話を執筆しようと思います。
我々が思っている以上に細菌は賢く、我々がいかに細菌のことを知らないか、お伝えできるのではないかと思います。
免疫と感染に関するコラム


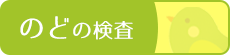
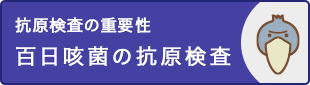
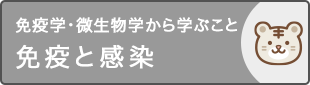
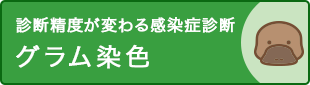
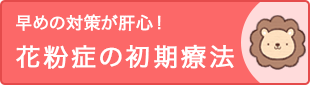
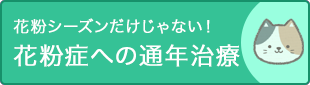

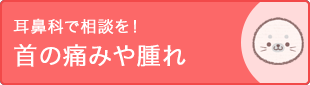
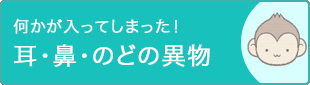
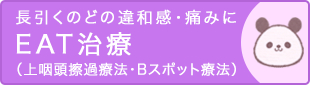
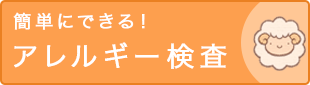
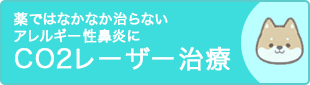
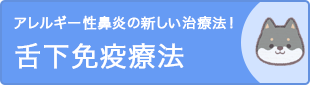
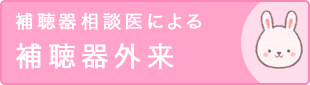
- 耳の病気
- 急性中耳炎
- 慢性滲出性中耳炎
- 良性発作性頭位めまい症
- メニエール病
- 突発性難聴